�N�����ǎ҂́u�s�K���s���v�ƃR�~���j�P�[�V�����\�͂Ɋւ��镪�́@
�]�{��w�Z�̑��Ɛ��̎��Ԕc���Ɋւ���A���P�[�g���ʂ���]
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��s���S�㒹�{��w�Z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����F��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�X�X�V�N�P�P���Q�Q��
�@���{���̈�{��w�Z�̒��w�����Ɛ�(�N��͈�18�`54��)�ɂ��āA�A���P�[�g�ɂ��t�H���[�A�b�v�������s�����B�Ґ���254���ŁA���̂����u���ǁv�Q�́u�s�K���s���v�ƃR�~���j�P�[�V�����\�͂Ƃ̊֘A�ɂ��āA�u���_�x�v�Q����сu�_�E���ǁv�Q�Ɣ�r���A�������s�����B���̌��ʁA�u���ǁv�Q�ł͎v�t���㔼����N���ɂ����ĂS�l�ɂЂƂ�̊����ʼn��炩�́u�s�K���s���v��������X���ɂ������B����ɁA�u���_�x�v�Q����сu�_�E���ǁv�Q�ł͂��Ƃ�g�U��Ȃlj��炩�̕��@�ł̈Ӑ}�̕\�o��`�B�̔\�͂�L����Ȃ�u�s�K���s���v�̌����銄�������Ȃ��Ȃ��Ă����̂ɑ��āA�u���ǁv�Q�ł͍����Ȃ��Ă���ꍇ�̂��邱�Ƃ��������ꂽ�B�܂��A���ƂȂ����g�U��Ȃǂ̃R�~���j�P�[�V�����\�͂�L���Ă���ꍇ�A�u�s�K���s���v�̂������オ�\���ł�����̂����邱�Ƃ��������ꂽ�B
�L�[�E���[�h�F�A���P�[�g�����@���ǁ@�R�~���j�P�[�V�����\�́@�s�K���s��
�T. �͂��߂�
�@���ǂɊւ��錤����1943�N��L.Kanner�ɂ��u��I�ڐG�̎��I��Q(Autistic disturbances of affective contact)�v�̔��\�ȗ��̗��j���������Ă��Ȃ��B�N���̎��ǂɊւ��Ă��������̏Ǘጤ����ǐՌ����Ɍ����Ă���B�����̏����̗\�㌤���ɂ����ẮA���ǂ�L����҂�60���`70���ɂ��Ă͈�ʓI�ɗ\��͗ǍD�ł͂Ȃ�(Kanner et al.,1972;Lotter,1974;Gillberg & Steffenburg,1987)�Ƃ���A�Љ���ɓK��������A�d����w�ƂŖ����̂����������ł��Ă���̂͑S�̂�10���`15���ɂ����Ȃ�(Adams & Sheslow,1983)�Ƃ��ꂽ�B�������A����n��ɂ��Љ�x�ʂł̐���̂�������A���ɋ���╟���Ɋ֘A��������̎{��̏[���ɂ��A�ŋ߂̗\�㑜�ɂ��ω��������Ă��Ă���B�킪���ɂ����āA1990�N��ɓ����ď��т�ɂ���ċ�B�ƎR���n��ɂ����鎩�ǎ҂̗\�㒲�����s���Ă���(Kobayashi et al.,1992)�B����ɂ��ƁA�����ΏۂƂ������ǎ҂͔N��͈�18�`33��201���ł���A�U�Ύ��_�ł̔��B�̏�IQ70�ȏオ24�����߁A���y�x�҂�50���ȏ�ł������B�������ʂɂ��ƁA�ނ�̂���27�������A�E��i�w�ȂǂŎЉ�I�Ȏ����̉\���������Ă����B�܂��A�S�̂�78���قǂ����Ƃł̗������\�ł���A���S�̂�54���قǂ͎Љ���ւ̓K���������Ă����B
�@���ǂ�70���`80���͐��_�x���������Ă���Ƃ����(Rutter & Schopler,1987)�B����A���_�x�̏d�Ǔx���d���Ȃ�قǎ��X�����Ƃ��Ȃ����Ƃ������Ȃ�A�d�x�̐��_�x�ł�42���A�ŏd�x�̏ꍇ��86���̊����Ŏ��X����������Ƃ��������B���X�����Ƃ��Ȃ����_�x�̏d�Ǔx���d�x�ł���^�C�v�̏�Q�ɂ��ẮA���ǂ��ꎟ�I�ȏ�Q�œI�ɒm�\�̔��B�����Ȃ�ꂽ���̂��A���_�x���ꎟ�I�ȏ�Q�œI�Ȍ��ʂƂ��Ď��X�������悤�ɂȂ����̂��͍����ł͕����čl���Ă��Ȃ��B�����ł͂Ȃ��āA�]��Q�̍L����̒��x�ɂ���Đ��_�x�̍����̒��x���قȂ�ƍl�����Ă���(����,1995)�B
�@���̂悤�Ȏ��ǂɊւ��Ďv�t���ȍ~�̖��Ƃ��Ă͂��܂��܂ȁu�s�K���s���v����������B�����́u�s�K���s���v�́A�̊i���傫���Ȃ�̗͂������ɂƂ��Ȃ����x��댯�����ُ�ɑ�������B���Ƃ��A�U���s���Ɋւ��ėc���ɂ�������Ă��������邱�Ƃ����邪�A�����������ł����Ă��N�ɂ��������Ƃ���͖Y�ꂪ�����L���Ɏc����̂ƂȂ邱�Ƃ�����B
���ǎ����܂߂����B��Q���̂��܂��܂ȁu�s�K���s���v�Ɋւ��ẮA�����̋@�\�͂��邱�Ƃɂ���ċ@�\�I�ɓ����Ȕ����N���X���`�������邱�Ƃɂ��A���Y�u�s�K���s���v��]�܂��������֕ω���������g�݂��s���Ă���(Carr,1988)�B���̍ۂɌ`�������@�\�I�ɓ����Ȕ����N���X�ɃR�~���j�P�[�V�����@�\����ՂɎ����������g�݂�����Ă���B�܂�A�u�s�K���s���v���̂��̂͂܂��������삳��Ȃ��ɂ�������炸�A�R�~���j�P�[�V������������������ɂ�ē��Y�u�s�K���s���v�̌����������邱�ƂɂȂ�(�u�����ʉ��v)�B�K�ȃR�~���j�P�[�V�����s�����I������A���ꂪ�@�\�I�ɗp����ꂽ�Ȃ�A���펙�ł����B��Q���ł��u�s�K���s���v�͌������Ă������Ƃ�����܂łɊώ@����Ă���B
�@���V��(1995)�́u�s�K���s���v�Ƌ@�\�I�ɓ����ȉ����v���s���Ƃ��ẴJ�[�h�̎g�p(�J�[�h���w�����A�J�[�h�������Ď���)�Ɓu�������āv�̉�������̎g�p�ɂ���č���ۑ肩��̓����s�����ጸ�������Ƃ���Ă���B���̂悤�ɁA�I�������R�~���j�P�[�V�����s���̃��[�h�̓J�[�h��g�U��Ȃǂ̎��o�I�Ȃ��̂�A���ƂȂlj����ɂ�钮�o�I�Ȃ��̂��l������B�����āA���̂悤�ȓK�ȃ��[�h���͂��߃R�~���j�P�[�V�����̎w���₻�̕��@�ɂ��ẮA����ƂƂ��Ɂu���L�͈͂̐l�ɕ��G�ȍl����`���邱�Ƃ��ł��鎩�R���݂Ȍ���V�X�e���̑��i�v����u�ǂ�ȕ��@�ł��낤�Ɛe�����l�X�ɂł��邾�������A���m�ɓ`�B�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��鉇���v�ւƈڍs���Ă���(Lord & O'Neill,1983;����,1993)�B
�@����A����̈�{��w�Z�̑��Ɛ���Ώۂɑ��ƌ�̐����ɂ��Č���̃A���P�[�g�������s���A��������N�����ǎ҂́u�s�K���s���v�̏ƃR�~���j�P�[�V�����\�͂̊֘A�ɂ��Č������s�����B�ΏƌQ�Ƃ��ē����{��w�Z�̑��Ɛ��̂����u���_�x�v�Q�Ɓu�_�E���ǁv�Q�����グ�A��r�������s�����B����ɁA�������玦�����������Ɋ�Â��ĐN���ȑO�ɁA���Ɋw����ŋ��߂���w���ɂ��Č������s�����B
�U. ���@
�P. �Ώێ�
�@���{���l�{��w�Z���Ɛ���ΏۂɌ��݂̐����ɂ��ăA���P�[�g�ɂ����Ԓ������s�����B�Ȃ��A�l�{��w�Z�͏��w������ђ��w������Ȃ�{��w�Z�ł���A���������Ē��w�����Ɛ��̂����i�w�҂͑��̗{��w�Z�������i�w���邱�ƂɂȂ�B�Ώێ҂����̗{��w�Z�P�Z�̑��Ɛ��Ɍ��肵�����R�Ƃ��Ď��̂��Ƃ���������B�܂��A����ł͒n��ɂ���ĕ����s���̎��ۂɂ͂����炩�̂ւ����肪�����邽�߁A���R����͂��ꂼ��̒n��(�s���P��)�ɋ��Z�����Q���҂̐����ɂ����炩�̏̍��ق�������ƍl������B���������āA�Ώۂ�{��w�Z�P�Z�̑��Ɛ��Ɍ��肷�邱�Ƃɂ���Ă��̋��Z�n�����肵�A�s�����x������̔ނ�̐������Ԃւ̉e���̕ϐ���������x�����ł���ƍl������B�Q�߂̗��R�Ƃ��āA�{��w�Z�݊w���̋�����ʂȂ����È���ʂɂ�鍷�ق̉e����������x�������邱�Ƃ��\�ł���ƍl������B�����Ȃɂ���ċ���w���̊�b�ƂȂ�w�K�w���v�̂��쐬����Ă��邪�A���ۂ̋���ے��̍쐬�ɂ��Ă͊e�{��w�Z�̓Ǝ��̍l���Ɋ�Â��Ƃ��낪�傫���̂�����ł���B���������āA�{�i�I�ȐE�Ǝw���̂͂��܂�ȑO�̋`�����ے��̒��w���̑��Ɛ��ɑΏۂ���肷�邱�Ƃɂ���āA�݊w���Ԓ��̋���Ȃ����È炪����ڂ��e���ɂ��Ă�����x�̓������\�ƍl������B
�Q. ��������
�������ڂ͈ȉ��̒ʂ�ł������B
���N��A���ʁA����
����Q�F���ǁA���_�x�A�_�E���ǂɕ��ނ����B�u���ǁv�Q�Ɋւ��ẮA�Z��쐬�̃J���e��W�҂̋L���ɂ��A�Љ�I���ݍ�p�̏�Q�A����I����є�I�R�~���j�P�[�V�����\�͂̏�Q�A����ѓ���̑Ώۂɂ��Ă̂������Ȃǂ̍s���ُ̈�̂R�̎咛��̌���ꂽ�҂ł���A���Ȃ��Ƃ�����36�J���ȑO�ɂ͂���炪�����Ă����҂ł������B�ނ�͑S���A���݂̐f�f��ł���DSM-�W�̊�ɓK�����Ă����ƍl������B�܂��A�u���_�x�v�Q�Ɋւ��ẮADSM-�W�́u���_�x�v�̐f�f��ɓK�������҂ł���B
�����B�F���w�����Ǝ��_�ł̏��y�x�A���x�A�d�x�A�ŏd�x�ɕ��ނ����B���ނ́A�u�È�蒠�v�̔���( A , B1 , B2 )�ɂ�����B���Ȃ킿�A�u�y�x�v�́uB2�v����A�u���x�v�́uB1�v����A�u�d�x�v�́uA�v����Ƃ����B�Ȃ��A�uA�v����̂����A�����̋L�^���猾��I����є�I�R�~���j�P�[�V�����\�͂�L�����A���Љ�ɒ���������������Ă����҂ɂ��Ắu�ŏd�x�v�Ƃ����B
���R�~���j�P�[�V�����\�́F�ȉ��̂S���x���Œ������s�����B
�@�@�@�u���Ƃł̂��Ƃ肪�s���R�Ȃ��ł���v
�@�@�@�u�P��ɂ��A���邢�͂��Ƃɂ��[���łȂ����v
�@�@�@�u�������Ȃǂʼnv
�@�@�@�u�ł��Ȃ�(�܂��̎҂��悤���Ȃǂ���v���f����)�v
���u�s�K���s���v�̏F�ȉ��̂S���x���Œ������s�����B
�@�@�@�u�ߋ��ɂ������Ȃ��������A���݂������Ȃ��v
�@�@�@�u�ߋ��Ɍ���ꂽ���A���݂͌����Ȃ�(��������)�v
�@�@�@�u���݁A������v
�@�@�@�u���݁A���ɍ����Ă���v
�@�Ȃ��A�����̑ΏۂƂ����u�s�K���s���v�͎���12��ނ̍s���ł������B
�E�Љ�I�ɂ��d�ēx����������
�����A�U���s���A�j��s���A���Љ�I�s��
�E�����㍢����邪�A�d�ēx�͂��Ⴂ�ƍl���������
��A�p�j�b�N�A��s����A�������A�ΐH�A�����A�퓯�s���A����
�R. �������@
�@�l�{��w�Z���w�����Ƃ̂P����(1960�N�x)����36����(1996�N�x)�܂ł̑��Ɛ��̂����A�u���Ɛ��ی�҉�v�ɓ���Ă���ґS��(348��)��ΏۂɃA���P�[�g�p����z�z(�X��)���A��ԑ��Ŏ�����B�A���P�[�g�p���ւ̉͗��e���͂��߂��̗È�ɂ����Ƃ��������̐[���҂��L�����s�����B�Ȃ��A�{�{��w�Z�́u���Ɛ��ی�҉�v�͖{�{��w�Z���w�����Ɛ��̕ی�҂̔C�ӂ̉����ɂ���ł���B�P�����Ɛ��ȍ~�̖{�{��w�Z���w�����Ɛ��̑�����812���ł���A���������āu���Ɛ��ی�҉�v�ւ̉�������42.9���ƂȂ��Ă���B
�@�������Ԃ́A1996�N10��30�����瓯�N11��10���ł������B
�V. ����
�@�A���P�[�g�p���̔z�z�Ώێґ�����348���ł���A�Ґ���254���ł������B�������73.0���ł������B
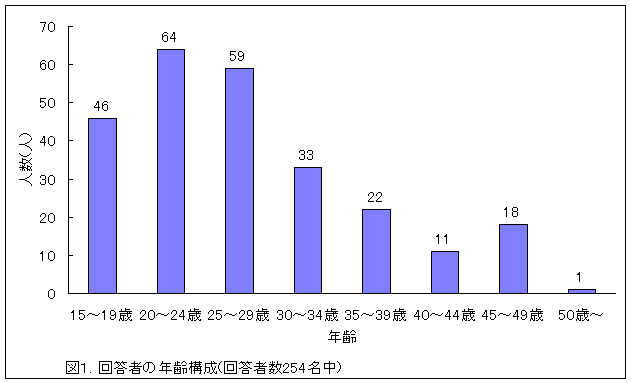
�@�҂̔N��\��(�}�P)�́A34�Έȉ��̐l���̍��v���S�̂�79.5�����߂Ă����B
�@���ɁA�҂̏�Q�ʐl���𒆊w�����Ǝ��_�ł̔��B�̏��Ƃɐ}�Q�Ɏ����B�܂��A�u���ǁv�Q�A�u���_�x�v�Q�A�u�_�E���ǁv�Q�ɂ��Ă����̔��B�̏��Ƃ̐l���̊�����}�R�Ɏ����B�u���ǁv�Q�ɂ����āA�u�d�x�v�Ɓu�ŏd�x�v�̎҂̐�߂銄����76.5���ɂ̂ڂ�A���̂Q�Q�����������Ƃ��킩��B���Ȃ݂ɁA�u���_�x�v�Q��46.0���A�u�_�E���ǁv�Q��54.6���ł������B
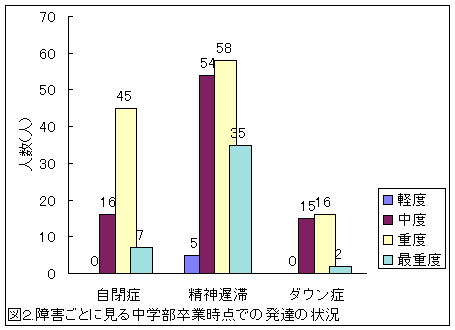
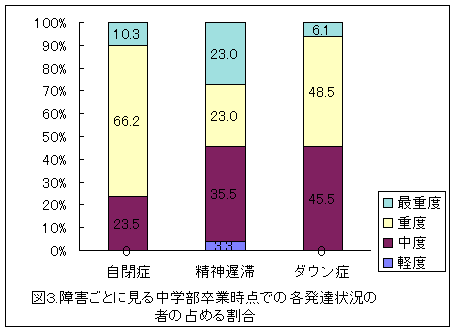
�@�e��Q�Q�ɂ����Č��݂��ꂼ��́u�s�K���s���v�̌����銄����}�S�Ɏ����B�������s����12��ނ́u�s�K���s���v���ꂼ��ɂ��āA��������҂̂��̏�Q�Q�̐l���S�̂ɑ��Đ�߂銄������Q���Ƃ́u�s���o�����v�Ƃ��ĎZ�o�����B���̌��ʁA�u�s���o�����v�̕��ς́u���ǁv�Q��24.4���A�u���_�x�v�Q��10.1���A�u�_�E���ǁv�Q��7.3���ł������B�u���ǁv�Q�ɂ����Ă͉��炩�́u�s�K���s���v�����ƌ�ɂ����Ă������銄���������Ƃ������A���ς���ƂS�l�ɂЂƂ�̊����Ō��݂������邱�ƂɂȂ�B
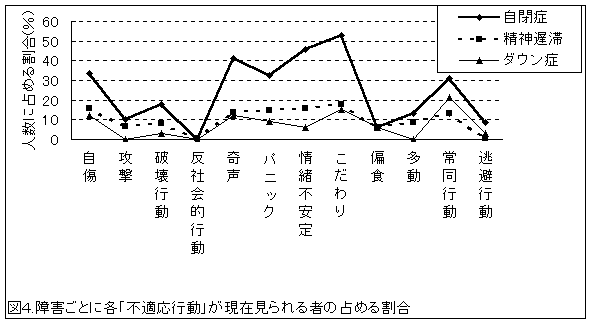
�@���ɁA�e��Q�Q�ɂ��āu�s�K���s���v�ƃR�~���j�P�[�V�����\�͂Ƃ̊W�ׂ��B���̍ہA�u���ǁv�Q�ɂ����Ắu�s���o�����v��30���ȏ�́u�s�K���s���v��ΏۂƂ��Ď��グ�邱�ƂƂ����B���Ȃ킿�A�u�������(52.9��)�v�A�u��s����(45.6��)�v�A�u�(41.2��)�v�A�u����(33.8��)�v�A�u�p�j�b�N(32.4��)�v�A�u�퓯�s��(30.9��)�v������ɊY�������B�܂��A���̂Q�Q�Ɋւ��Ắu�s���o�����v�̍����������ʂR�ʂ܂ł́u�s�K���s���v�����グ���B���Ȃ킿�A�u���_�x�v�Q�ł́u�������(17.8��)�v�A�u��s����(15.8��)�v�A�u����(15.8��)�v�ł���A�u�_�E���ǁv�Q�ł́u�퓯�s��(21.2)���v�A�u�������(15.2��)�v�A�u����(12.1��)�v�A�u�(12.1��)�v�ł������B
�@�܂��A�u���ǁv�Q�Ɋւ��āA�����̂U��ނ́u�s�K���s���v�̌��݁u������ҁv�Ɓu�����Ȃ��ҁv�̃R�~���j�P�[�V�����\�͂Ƃ̊W��}�T�A�}�U�A�}�V�Ɏ������B�}�T�̓R�~���j�P�[�V�����\�͂��u���Ƃʼnv�̎҂Ɋւ�����̂ł���B��������A���Ƃ�p���Ď����̗v����Ӑ}��\�o���邢�͓`�B���邱�Ƃ��ł���ƁA�����́u�s�K���s���v�������Ȃ��҂̕����������Ƃ��������B�܂��A�u�������v�Ɋւ��ẮA�u������ҁv�Ɓu�����Ȃ��ҁv�̐�߂銄���͓����ł���A���Ƃŕ\�o���ł���Ɓu�������v�������Ȃ��Ƃ͕K������������Ȃ����Ƃ������ꂽ�B�}�U�̓R�~���j�P�[�V�����\�͂��u�g�U��Ȃǂʼnv�̎҂Ɋւ�����̂ł���B��������A���Ƃłł��Ȃ��Ƃ��g�U��₵�����ȂǂŎ����̗v����Ӑ}��\�o���邢�͓`�B�ł���ƁA�����̂U��ނ́u�s�K���s���v�̂����A�u�������v�A�u��s����v�A�u��v�Ɋւ��Ắu������ҁv�̕����������Ƃ������ꂽ�B����A�u�����v�A�u�p�j�b�N�v�A�u�퓯�s���v�Ɋւ��Ắu�����Ȃ��ҁv�̕����������Ƃ������ꂽ�B�}�V�͂�����̕��@�ł��R�~���j�P�[�V�����̎�i�������Ȃ��҂Ɋւ�����̂ł���B��������́A�u������ҁv�̕����u�����Ȃ��ҁv���������悤����������悤�ł���B�������A���̃R�~���j�P�[�V�����\�͂ɊY������҂̐l�������Ȃ��A�܂��u������ҁv�Ɓu�����Ȃ��ҁv�Ƃ̍����e�u�s�K���s���v�ŏ��������߂ɁA���炩�̊W�����ނ��Ƃ͍���ł���ƌ�����B
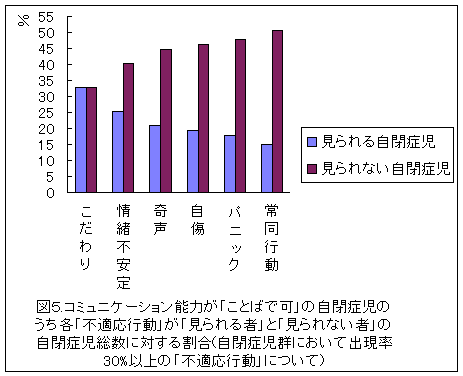
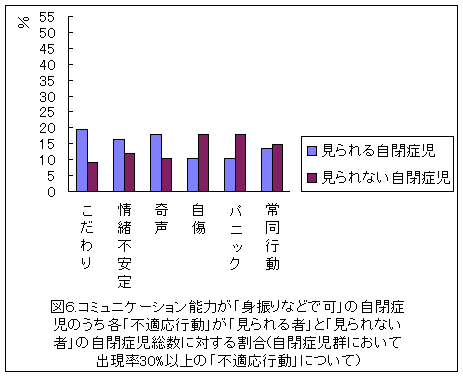
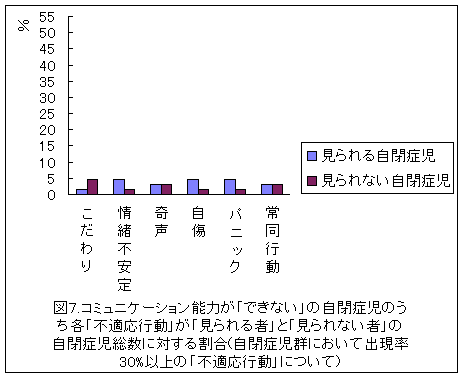
�@���ɁA�}�W�A�}�X�A�}10�́u���_�x�v�Q�ɂ��Ċe�R�~���j�P�[�V�����\�͂Ɓu�s�K���s���v�Ƃ̊W�����������̂ł���B�}�W�Ɛ}�X����A�u���_�x�v�Q�ɂ����ẮA���ƂȂ����g�U��₵�����Ŏ����̗v����Ӑ}���\�o�Ȃ����`�B�ł���Ƃ����́u�s�K���s���v�́u�����Ȃ��ҁv�̕����������Ƃ������ꂽ�B�܂��A�}10����́A������̕��@�ł��R�~���j�P�[�V�����̎�i�������Ȃ��Ă��A�e�u�s�K���s���v�́u�����Ȃ��ҁv�̕��������悤�ł���B
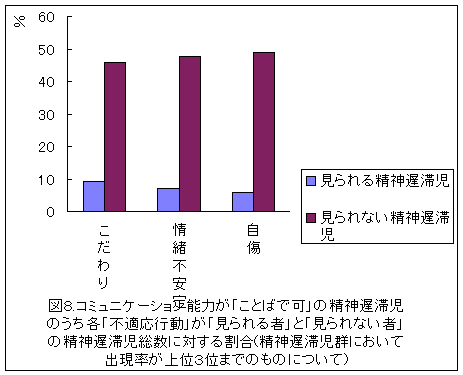
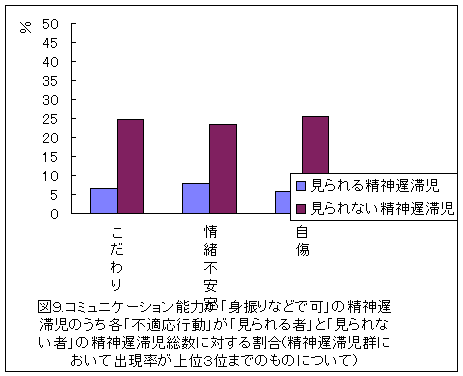
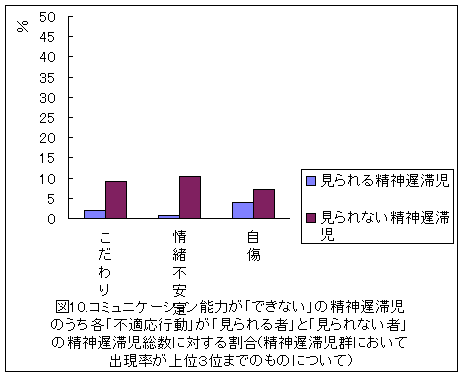
�@����ɁA�}11�A�}12�A�}13�́u�_�E���ǁv�Q�ɂ��Ċe�R�~���j�P�[�V�����\�͂Ɓu�s�K���s���v�Ƃ̊W�����������̂ł���B
�}11�Ɛ}12����A�u�_�E���ǁv�Q�ɂ����Ă��A���ƂȂ����g�U��₵�����Ŏ����̗v����Ӑ}��\�o�Ȃ����`�B�ł���ƁA�����́u�s�K���s���v�́u�����Ȃ��ҁv�̕����������Ƃ������ꂽ�B�܂��A�}13����́A������̕��@�ł��R�~���j�P�[�V�����̎�i�������Ȃ��҂́A���͏��������̂ł��邪�����́u�s�K���s���v���u������ҁv�̕��������悤����������悤�ł���B�������A�u���ǁv�Q�̏ꍇ�Ɠ��������̃R�~���j�P�[�V�����\�͂ɊY������҂̐l�������Ȃ��A�܂��u������ҁv�Ɓu�����Ȃ��ҁv�Ƃ̍����e�u�s�K���s���v�ŏ��������߂ɁA���炩�̊W�����ނ��Ƃ͍���ł���ƌ�����B
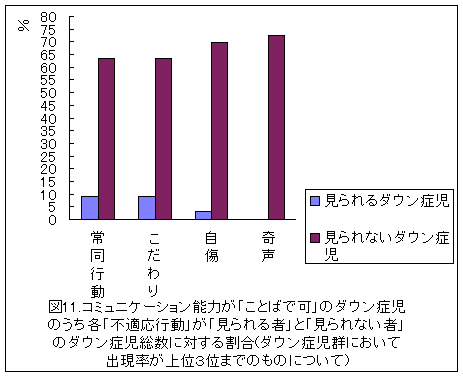
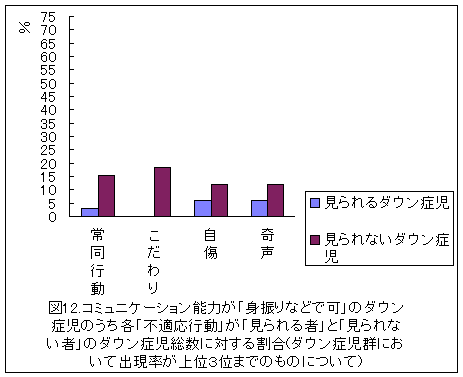
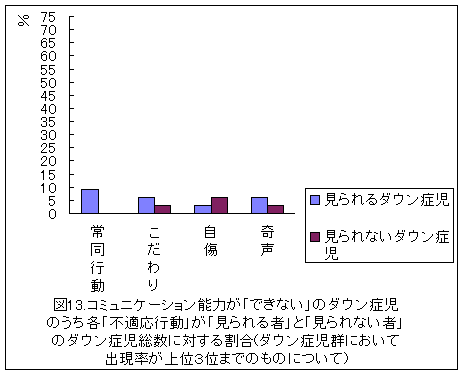
���ɁA��������12��ނ́u�s�K���s���v�Ɋւ��āA�u�ȑO�Ɍ���ꂽ���A���݂͌����Ȃ�(��������)�v�Ɖ����҂Ɋւ��āA��Q�Q���Ƃɐ�߂�l���̊�����}14�Ɏ������B�u���ǁv�Q�ł́u����(26.9%)�v�A�u�ΐH(20.9%)�v�A�u�p�j�b�N(19.4%)�v�A�u����(14.9%)�v�A�u�j��s��(13.4%)�v�̏��Ɂu���������v�Ƃ���҂̊��������������B�u���_�x�v�Q�ł́u����(8.7%)�v�A�u�(8.7%)�v�A�u����(5.3%)�v�A�u��s����(5.3%)�v�A�u�p�j�b�N(4.7%)�v�̏��ŁA�u�_�E���ǁv�Q�ł́u�p�j�b�N(6.1%)�v�A�u�ΐH(6.1%)�v�A�u�j��s��(3.0%)�v�A�u����(3.0%)�v�A�u�퓯�s��(3.0%)�v�̏��Łu���������v�Ɖ����҂̐�߂銄�������������B
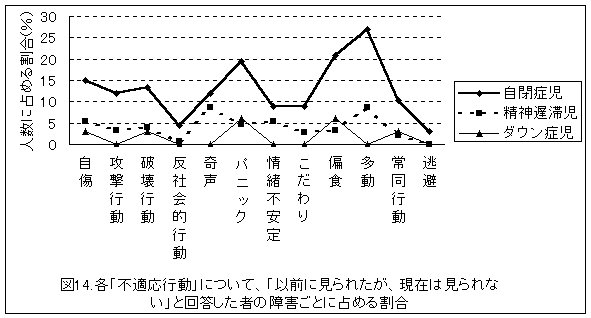
�܂��A�����̏��������u�s�K���s���v�ɂ��āu���������v�Ɖ����҂̃R�~���j�P�[�V�����\�͂��u���ǁv�Q�ɂ��Ă͐}15�ɁA�u���_�x�v�Q�ɂ��Ă͐}16�Ɏ������B
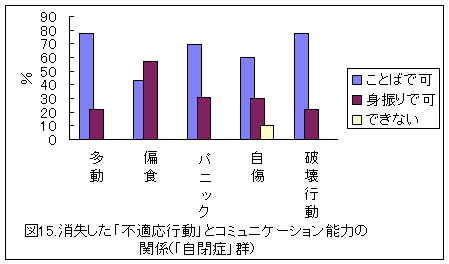
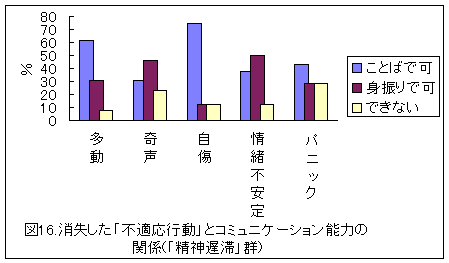
���̌��ʁA�u���ǁv�Q�ɂ��ẮA�u�����v�������Ă�����́u�s�K���s���v�Ɋւ��Ă��҂͂��ׂĂ��ƂȂ����g�U��Ȃǂł̃R�~���j�P�[�V�����\�͂�L���Ă����B�u���_�x�v�Q�ɂ��ẮA����I���邢�͔�I�R�~���j�P�[�V�����\�͂�L���Ȃ��ꍇ�ɂ��u���������v�Ɖ����҂��������B
�W. �l�@
�u���ǁv�Q�ł́A���w�����Ǝ��_�ł̔��B�̒��x���d�x����эŏd�x�ł������҂̐�߂銄����76.5���ł���A�u���_�x�v�Q��46.0���A�u�_�E���ǁv�Q��54.6���ɂ���ׂč����Ȃ��Ă����B�܂��A��������12��ނ́u�s�K���s���v�̌��݂́u�s���o�����v�̕��ς��u���ǁv�Q�ł�24.4���ł���A�u���_�x�v�Q��10.1���A�u�_�E���ǁv�Q��7.3���Ƃ���ׂ�ƍ����Ȃ��Ă����B��������A�A���P�[�g�҂̂����u���ǁv�Q�ɂ��ẮA�u���_�x�v�Q����сu�_�E���ǁv�Q�������w�����Ǝ��_�ł̔��B�̒��x�����d�x�ł���A�����݂ł��u�s�K���s���v�̏o���������Q�̏�Q�Q�����Q�{�ȏ�̊����Ō����邱�Ƃ��������ꂽ�B
�@���܂��܂ȁu���s���v�ւ̑Ώ��̕��@�Ƃ��āA�u�@�\�I�������v�ɂ�锽���ʉ��ɂ���ē��Y�u���s���v�̏o�������������Ă������g��(Carr,1988)���Ȃ���Ă���B�����ŁA�ȉ��ɏ�L�́u���ǁv�Q�Ɋւ��Č��݂̃R�~���j�P�[�V�����\��(�����Ɏ����̗v����Ӑ}�̕\�o�Ȃ����`�B�̔\��)�Ɓu�s�K���s���v�̏o���̊W�ɂ��Č������s���B�ΏۂƂ��Ắu�s�K���s���v�́u�s���o�����v��30�����z�����u�������v�A�u��s����v�A�u��v�A�u�����v�A�u�p�j�b�N�v�A����сu�퓯�s���v�ł���B�܂��A��r�Q�Ƃ��Ắu���_�x�v�Q�ł́u�������v�A�u��s����v�A�u�����v���u�_�E���ǁv�Q�ł́u�퓯�s���v�A�u�������v�A�u�����v�A�u��v�����グ��(�����̏�Q�Q�ɂ����Ắu�s���o�����v����ʂR�ʂ܂ł̂��̂ł���)�B
�܂��A�P�ꂠ�邢�͂��Ƃɂ���Ă�����x�����̗v����Ӑ}���\�o�Ȃ����`�B�ł���҂ɂ��ẮA�u���ǁv�Q�A�u���_�x�v�Q�A�u�_�E���ǁv�Q�̂�����ɂ����Ă��u�s�K���s���v�������Ȃ��ꍇ�̕������������B����́A����I�ȃR�~���j�P�[�V�����V�X�e�����l�����邱�Ƃ͎Љ�I�X�L�������߁A�W�c�����ɂ��K�����邱�Ƃ���肽�₷�����Ƃ������Ă���B�܂��A�P��Ȃ������Ƃł̃R�~���j�P�[�V�����\�͂�L���Ă��鎩�ǎ��҂́u�������v��������ꍇ�ƌ����Ȃ��ꍇ���Ƃ��ɓ������x���邱�Ƃ��������ꂽ�B�u�������v�́u���ǁv�ɓ����I�ȏ�Q�Ƃ��Č���I�R�~���j�P�[�V�����\�͂��l�����Ă��Ă��Ȃ�����30�����ɂ����Č����邱�Ƃ��������ꂽ�ƌ�����B
�@���ɁA���Ƃ�g�U����͂��߂��̑��̉��炩�̕��@�ɂ���Ă������̗v����Ӑ}��\�o���邱�Ƃ��ł����A��ɂ܂��̎҂����l�����Ĕ��f���Ă����K�v�̂���҂ɂ��ẮA�u���ǁv�Q����сu�_�E���ǁv�Q�ɂ����āu�s�K���s���v�̌�����ꍇ���킸���ł��邪���������B����́A�����̏�Q�Q�ɂ����Ă͗v����Ӑ}�̕\�o��i��L���Ȃ��ꍇ�ɂ́u�s�K���s���v�Ƃ����`�ł�����\�����₷�����Ƃ��������Ă���B�������A�u���_�x�v�Q�ł́A�����̗v����Ӑ}��\�o�ł��Ȃ��Ă��A�����́u�s�K���s���v���������ɏɓK�����Ă���҂������ƍl������B
�@�Ō�ɁA���Ƃ�P��ɂ���Ă͎����̗v����Ӑ}��\�o�Ȃ����`�B�ł��Ȃ��Ă��A�g�U��₵�����łȂ�\�ł���҂̏ꍇ�ɂ��čl�@����B�A���P�[�g�����̌��ʂ���́A�u���_�x�v�Q�Ɓu�_�E���ǁv�Q�ɂ��Ắu�s�K���s���v�̌����Ȃ��ꍇ�̕������������B����͉��炩�̃R�~���j�P�[�V�����V�X�e�����l�����Ă���ƏW�c�����ւ̓K���̉\�����傫���Ȃ邱�Ƃ������Ă���B����A�u���ǁv�Q�ł́u�������v�A�u��s����v�A�u��v�Ɋւ��Ă͂��̂悤�ȃR�~���j�P�[�V�����V�X�e�����l�����Ă���҂ł͌�����ꍇ���������Ƃ��������ꂽ�B
�@��ʂɁA�u�s�K���s���v�̊�Ղɉ��炩�̃R�~���j�P�[�V�����@�\��z�肷��Ȃ�A�����̗v����Ӑ}�����炩�̕��@�ŕ\�o�Ȃ����`�B�ł���ꍇ�ɂ́u�s�K���s���v�������Ȃ��悤�ɂȂ�ƍl������B�{�A���P�[�g�����ɂ����Ă��A�u���ǁv�Q�A�u���_�x�v�Q�A�u�_�E���ǁv�Q�ɂ����āA���Ƃ�P��Ŏ����̗v����Ӑ}���\�o�Ȃ����`�B�ł���҂ɂ��Ă͂��̂悤�ȌX�����m�F�ł����B�܂��A���ƂłȂ��Ƃ��g�U��₵�����łȂ玩���̗v����Ӑ}��\�o�Ȃ����`�B�ł���Ȃ�A�u���_�x�v�Q�Ɓu�_�E���ǁv�Q�ɂ����Ă͂��̌X�����m�F�ł����B����A�u���ǁv�Q�ɂ����ẮA�g�U��₵�����ł̕\�o�Ȃ����`�B�\�͂����҂Ɋւ��āu�s�K���s���v�̌����邱�Ƃ������Ȃ�ꍇ���������ꂽ�B
�@���̗��R�Ƃ��Ď��̂悤�ɍl���邱�Ƃ��ł���B��ʂɁA���ǎ��͂��鎖���𑼂̕��ő�u��������(�u�E�������v)�A�ӂ�V�т̏œ_���������g���玩���ȊO�̎҂�l�`�ȂǂɈڂ�����(�u�E���S���v)�A�܂��f�ГI�ł������s�ׂ𑊌݂ɗL�@�I�Ɋ֘A�Â��Ă����A�̌n���������V�тւƍ\�����Ă���(�u�������v)���Ƃ�����(Cicchetti et al.,1994)�Ȃ��Ƃ���������B���̂��Ƃ́A�����̗v����Ӑ}�̓`�B�̕��@��`�Ԃ𑼂̂悭������ʂ�ɉ��p���ėp���邱�Ƃ�����ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B���������āA���ǎ��̃R�~���j�P�[�V�����w���ɂ����ẮA�F�m���B�ۑ�ɂ�鎩�R���݂Ȍ���V�X�e���̊l���Ɍ��������g�݂���A����̕��@��[�h�ɂ��m���ȓ`�B�V�X�e���̊l���ւ̎��g�݂ւƓ]�������߂���(Lord & O'Neil,1983;����,1993)�悤�ɂȂ�B
�@�{�A���P�[�g�����ɂ�����u���ǁv�Q�ɂ��Ă��A�\�o�Ȃ����`�B�̕��@�Ƃ��Ă̐g�U��Ȃ������������A��e�ȂǓ���̎҂݂̂������\�ȋɂ߂ē���Ȍ`�Ԃ��Ƃ��Ă���ꍇ�A���邢�͂��̂悤�ȕ��@������̏�ʂ�����ɂ����Ă̂ݗp��������̂ł���ꍇ���l������B���̌��ʁA��e�ȊO�̎҂ɂƂ��ẮA���邢�͓���̏����ȊO�̏ꍇ�ɂ͂��̐g�U��Ȃ����������̈Ӗ����������ꂸ�Ɂu�s�K���s���v�Ƃ��ĕ\�o����Ă��邱�Ƃ��l������B����A�u���_�x�v�Q�Ɓu�_�E���ǁv�Q�ɂ����ẮA����\�o�Ȃ����`�B�̕��@�𑼂̎�����ʂɂ����p���ėp���邱�Ƃ��ł�����A�g�U��₵�����ł̕��@�ȊO�ɂ��������牽�炩�̎肪����𗘗p���ăR�~���j�P�[�V�����̖ړI���B���\�ƂȂ��Ă���ꍇ�������ƍl������B
����ɁA�{�A���P�[�g�����̌��ʂɂ��ƁA�u���ǁv�Q�ɂ����Đg�U��Ȃ����������łȂ�v����Ӑ}��\�o�Ȃ����`�B�ł���ꍇ�A�u�������v�A�u��s����v�A�u��v�ɂ��Ắu�����Ȃ��v�ꍇ�����u������v�ꍇ�̕������������B�����̗v����Ӑ}���K�ɑ���ɓ`���Ȃ��ꍇ�A���A���̍ۂ̓`�B���悤�Ƃ���C�����������ꍇ�ɂ́A�u��v�Ƃ��ĉ��炩�̉����̕\�o���������Ƃ��l������ł��낤�B�܂��A���̂悤�ȏ́A��̕s����Ɏ��炵�߂邱�Ƃ��l������B����ɁA�v����Ӑ}���`���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�V���ȑI�������l������̂ł͂Ȃ��āA����e�������⊈���Ɏ������䂾�˂鎖�Ԃ���������ł��낤�B���̏ꍇ�ɂ́A�u�������v�Ƃ��Ă̍s���������邱�ƂɂȂ�B�u�����v��u�p�j�b�N�v�Ɏ���Ȃ��܂ł��A���̂悤�ȍs�������₷��������\���͏[���ɍl������B
���̂悤�ȁu���ǁv�Q�Ɋւ���A���P�[�g�����̌��ʂ���A�N���́u�s�K���s���v�ɑΉ����邽�߂ɂ́A���̂悤�ȋ���I�Ȏ��g�݂̕K�v�����l������B
�@�ЂƂ߂́A���Ƃɂ��R�~���j�P�[�V�����̃X�L�����l�������邱�Ƃł���B�ƒ됶����w�Z�����Ȃǂ̓��퐶���̏�ɂ����āA�P�ꃌ�x���A���邢�͊ȒP�ȕ����x���ł̗�������ѕ\�o�̃X�L�����l�����邱�Ƃ��ڎw�����B���炩�̌���I�R�~���j�P�[�V�����X�L�����l�����Ă���ƁA���҂̈Ӑ}�̗����⎩���̈Ӑ}�̕\�o�̉\�����g�傳��邱�ƂɂȂ邩��ł���B���邢�́A�g�U��Ȃǂ̔�I�Ȃ��̂̊l�����w���ڕW�ƂȂ邱�Ƃ��l������B�@
�@��Q�́A��I�ȃR�~���j�P�[�V�����V�X�e���̏ꍇ�́A�����ɂ��Ă܂��̂ł��邾�������̎҂����ʗ�����}�邱�Ƃ��K�v�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�����̔�I�R�~���j�P�[�V�����V�X�e���͓��قȌ`����邱�Ƃ��������߂ł���B�܂�ALord��(1983)���(1993)�̌����悤�ɁA�u����V�X�e���̊l���v����A����ƂƂ��ɁA�u����̕��@�œ���̑���ɓ`�B�\�ȃV�X�e���̊l���v�ւƃR�~���j�P�[�V�����X�L���̎w���̎��g�݂��ڍs�����Ă������Ƃ���ł���B����A�u���_�x�v�Q��u�_�E���ǁv�Q�ɂ����ẮA����I�Ȃ�тɔ�I�R�~���j�P�[�V�����X�L���̂���������N���́u�s�K���s���v�ւ̑Ή��ɏd�v�Ȗ������ʂ����ƌ�����B
��R�ɁA����ɂ��u�s�K���s���v�̌��オ������x�\���\�Ȃ��Ƃ��l�����邱�Ƃł���B���ɒ��w���܂ł̐����N��ɂ����āA�w���̏œ_�����́u�s�K���s���v�̌���ɒu���ꍇ�A���̎w��������ȊO�̗̈�ɑ��Ă����炷�e���ɂ��ď[���Ɍ������s���K�v�����邾�낤�B�Ȃ��Ȃ�A����́u�s�K���s���v�̌���Ɍ������w���ɂ���āA�����ʂɂ����ēI�ɂ��̑��́u�s�K���s���v���������Ă���\�����l�����邩��ł���B��̓I�Ɍ����A�u���ǁv�Q�ɂ����ẮA�u�����v�A�u�ΐH�v�A�u�p�j�b�N�v�ɂ��Ă͉���ƂƂ��Ɍ��シ��\�������̑��́u�s�K���s���v�ɂ���ׂč����ƌ�����B�܂��A�{�������ʂ���́A�����́u�s�K���s���v�̏��������u���ǁv�Q�ł́A���ƂȂ����g�U��Ȃǂł̃R�~���j�P�[�V�����\�͂�L���Ă���ꍇ���قƂ�ǂł��邱�Ƃ��������ꂽ�B
�y�����z
Adams W.V. & D.V.Sheslow(1983).�N���̔��B�I�ϓ_����̓W�].In E. Schopler & G.B.Mesibov(Eds.),Autism in adolescents and adults. New York:Plenum Press. �����W�E���c���F(�Ė�)(1987),�N���̎��� �l�����̊m��(pp.13-43).���w�p�o�Ŏ�.
Cicchetti D.,Beeghly M.,& Weiss-Perry B.(1994).Symbolic Development in Children with Down Syndrome and in Children with Autism:An Organizational,Developmental Psychopathology Per spective.In A.Slade & D.P.Wolf(Eds.),Children at Play(pp.206-237).New York:Oxford University Press.
Carr E.G.(1988).�����ʉ��̃��J�j�Y���Ƃ��Ă̋@�\�I������.In R. Horner et al.(Eds.),Generalization and Maintenance:Life-style Changes in Applied Settings. ���яd�Y�E�����N��(�Ė�)(1992),����,���B��Q�҂̎Љ�Q�����߂�����(pp.234-256).��r��.
Gillberg C.& Steffenburg S.(1987).Outcome and prognostic factors in infantile autism and similar conditions:A population-based study of 46 cases followed through puberty.Journal of Autism and Developmental Disorders,17,273-287.
���V�I�q�E�����`��(1995).���B�x�؎��̉ۑ��ʂɂ�������s���ւ̋@�\�I�R�~���j�P�[�V�����P���]�u�������̂��`�B���̌����].���ꋳ��w����,33,11-19.
Kanner L.,Rodriguez A.,& Ashenden B.(1972).How far can autistic children go in matters of social adaptation?.Journal of Autism and Childhood Schizophrenia,2,9-33.
���ї���(1995).���{�ĖE������㖾�E���䏁��(�ďC)(1995),���B�S���w���T(pp.290).�~�l�����@���[.
Kobayashi R.,Murata T.,& Yoshinaga K.(1992).A Follow-Up Study of 201 Children with Autism in Kyushu and Yamaguchi Areas,Japan. Journal of Autism and Developmental Disorders,22,395-411.
Lord C.& O'Neill P.J.(1983).���ǂ̐N�ɂ����錾��ƃR�~���j�P�[�V�����̃j�[�Y.In E.Schopler & G.B.Mesibov(Eds.),Autism in adolescents and adults.New York:Plenum Press. �����W�E���c���F(�Ė�)(1987),�N���̎��� �l�����̊m��(pp.67-93),���w�p�o�Ŏ�.
Lotter V.(1974).Social adjustment and placement of autistic children in Middlesex:A follow-up study.Journal of Autism and Childhood Schizophrenia,1,11-32.
Rutter M.& Schopler E.(1987).Autism and Pervasive Developmental Disorders:Concepts and Diagnostic Issues.Journal of Autism and Developmental Disorders,17,159-186.
�����N�v(1993).���ǂɂ�����V���{���@�\�`���̏�Q.�쑺�����E�ɓ��p�j�E�ɓ��ǎq(�ҏW),���ǂ̐f�f�Ɗ�b�I���(pp.209-239),�w����.