高学年部児童の個別目標設定に影響する要因について
金井孝明 1997/10/28
本校高学年部においては、本年度より朝の高学年全員による「合同集会(あるいは単に、「集会」)」を週1回にし、それ以外の日はその時間(つまり、登校時間である9時から、障害や発達レベルごとの縦割り集団によって取り組まれるグループ学習である「課題別学習」が始まる10時20分まで)を児童の学校生活での基礎集団であるクラスの時間として取り組んでいくこととした。本校のクラスは生活年齢に基づく編成であり、児童の持つ障害や発達の状況(さまざまな領域の発達のレベル)は、縦割り集団での学習である「課題別学習」とは異なり、同質ではない。
このようなクラスの時間の過ごし方は各担任に任されており、学年、クラスによりさまざまな過ごし方が試行されているのが現状である。この「時間の過ごし方」は言い換えれば「『児童の課題』を設定した取り組みがなされている」ことである。そして、この「児童の課題」とは個別目標が基礎にあり、そこから実際の取り組みは個別がいいのか、あるいはいくらかの集団がいいのかが決定される。そこにはひとりひとりの障害の状況や発達の状況といったような教育ならびに「療育」の重要な観点が考慮されることになる。
そこで、高学年児童の課題設定‐これは「個別課題」やそこから導き出される「集団での課題」を含んでいる‐に関して考慮すべき項目を児童の側面、保護者の側面、そして我々担当職員の側面に分けて考えてみた。
さまざまな意見や批判、その他感想などいただければ幸いである。
1.児童の側面[課題としての「発達の第二の急進期」]
高学年期は、障害のあるなしに関わらず、身体面および精神面での発達が著しい時期にある。10歳を過ぎる頃から急にこれまで着ていた服が小さくなってしまったり、靴が窮屈になってしまったりする。姿勢がこれまでに比べてしっかりしてきて、頭の位置が、したがって視線が上にあがってくる。そうすると人間の情報入力の80%〜90%を占めるとされる視覚情報の入力が量および質ともに進歩することとなる。それは当然精神面にも影響を与えることとなる。一般に言われる思春期が始まるのもこの時期である。このような時期を「発達の第二の急進期」と呼ぶ。ちなみに、「発達の第一の急進期」とは、5歳から6歳にかけての就学前後の時期を指している。
まず、身体面での変化についてみてみる。図1と図2は、本校児童生徒の最近6年間(1996年度まで)の年齢ごとの1年間の平均身長と平均体重の伸びあるいは増加を示している。
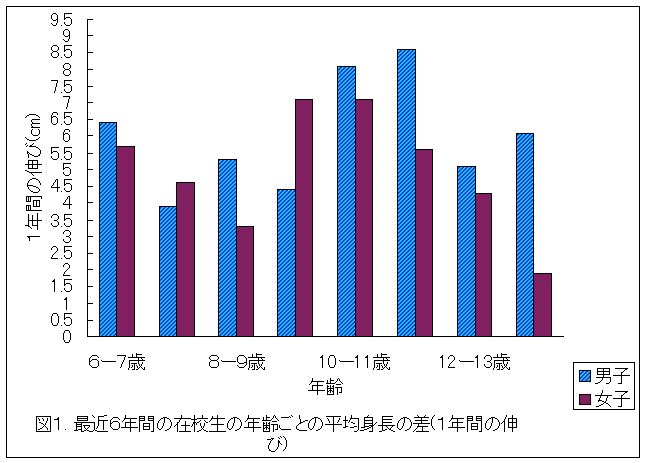
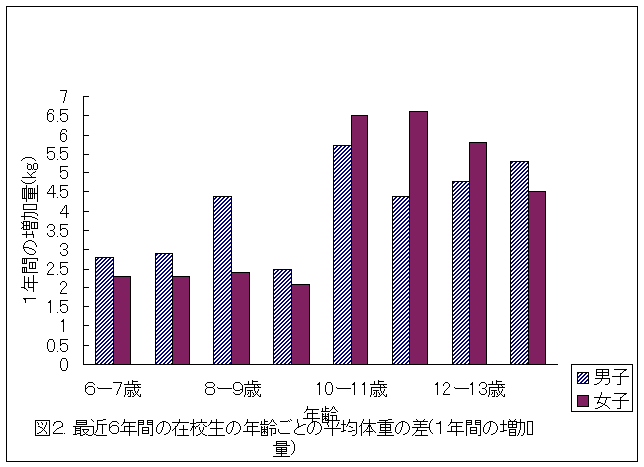
まず、身長(図1)に関しては、就学後と高学年の時期に伸びが大きいことがわかる。高学年においては、男子は女子よりも一年ほど遅れて伸びの大きい時期が訪れるようである。そして、女子の伸びはその後(つまり、中学部では)小さくなっていく。また、体重(図2)に関しては、男女とも高学年期から増加が急に大きくなっていることがわかる。そして、その増加は中学部に入っても続く。つまり、このような2つのグラフからは、高学年において児童は身体的に大きく成長することが本校においても見られることが示される。なお、ここで用いた数値は、障害種別になっていない。
一方、身体面の成長にはそれに見合うだけの適当な運動量が求められる。健常児のように自ら目的を持って運動に取り組むことがきわめて少ない本校児童にとって、これは大きな課題となってくる。先の2つのグラフから、高学年以降身長の伸びは鈍るが、体重の増加はそれほどに衰えないことがわかる。つまり、ここにいわゆる「肥満」傾向がはじまることになる。それも、平均すれば「高学年の時期から」ということになる。定期的に、意図的に身体を動かす機会を設定することが求められる。それはなにも高学年になったからそのような機会が必要だ、というのではなく、低学年の時期から、あるいはもっと以前からそのような習慣を計画的に身につけさせていく必要があるのだろう。
次に、精神的な成長に関してであるが、先ほども述べたように、おもに視覚を通じた情報入力が以前にもまして増えると考えられる。世の中が広く見えてくるのである。よく高学年期において、落ち着きが見られてきた児童、あるいは逆に、例えばこだわりが強くなったり、多動や他傷などが激しくなってたいへんになってくる児童が見られることがある。これはいずれも自分というものが確立されてきつつある段階と考えることができる。さまざまに存在し、飛び込んでくる情報に対して自分をどう位置づけたらいいのか、あるいはそれらから自分をどう守ればいいのか苦悩している姿なのである。このような形で自分というもの、つまり「自我」がはっきりと現れてくるようになる。そして、身体的な成長と相まって、その行動がこれまでよりも一段と影響力を持つようになるのである。こだわる子どもを動かすのに、これまでのように持ち上げて、ヒョイ、とはもはやいかないのである。このような場合、こだわりや他の「問題」とされる行動を「問題行動」とせずに、その基盤に持っている「機能(意味)」を理解することが大切である。そして、その上にその「機能」を別の表現方法で表すような力を身につけることが求められる。つまり、「自分」の考えていること、言いたいことをまわりの者(主に、大人)に伝える方法を持つことである。ここに、「コミュニケーション能力」をいかに意図的に獲得させていくかという重大な課題が子どもの側から突きつけられてくることになる。「自分を持つ」ということはこの子たちの人生の上でとてつもなく大きなできごとである。それは障害や発達のいかんを問わずひとりひとりちがった形で現わしてきている。それを敏感にキャッチしてやることが大切である。
しっかりしてきたり、あるいは「こまった」行動が見られてきたり、さまざまに行動に変化がでてくるのが高学年期のひとつの大きな特徴である。そのような変化に対しては、子どもの側の「自己有能感」というべきものをしっかりと育てる必要がある。「自己有能感」とは、簡単にいえば、自分はこれができるんだ、という自信である。しかし、それは自律性、自発性がないと育ってこないというのがE.H.エリクソンの言うところである。言うまでもなく、その基礎には信頼関係があることが必要である。
このような思春期に向けて、子どもの姿を個別に計画的に見ていくこと、そして、まず個別に適切な課題が計画的に設定されることが大切である。ひとりひとりについての適切な個別の課題が設定されてはじめて集団における課題ないし目標はその児童に対してあるいは対象の集団の成員に対して意味を持つようになる。
2.保護者の側面[課題としての「現状維持ないし安定態勢」の克服]
障害児を持った保護者、特に母親の心理的な状態は、一般的に乳幼児期における「ショック期」から、やがて「この子は障害など持っているはずがない」という「否認期」へと変化していく。そして、子どものまわりとのトラブルや、そのためのさまざまな病院めぐりという「混乱期」を経て、やがて「解決への努力期」、「受容期」へと変化を見せる。このような母親の心理的変化を仮定したとき、就学はどのような意味を持っているのだろうか。この時期には、もはや多くの親は「解決への努力期」あるいは「受容期」の心理状態であろうと考えていいだろう。しかし、このような心理状態に達した保護者にとってさえ、この子たちのこれからの姿や将来像、あるいはそのために求められる能力やスキルはどんなものなのか不安と期待でいっぱいのはずである。このことが学校教育への保護者のある意味での期待となり、保護者自身の励みともなるだろう。つまり、就学後の低学年期というのは将来の子ども自身の、あるいは子どもと保護者を含めた自分たちの姿を求めて期待と不安に満ちあふれた時期といえるだろう。学校教育への期待はきわめて大きい。あるいは我が子は字をおぼえて本でも読むようになるかもしれない、いろんなものが食べられるようになるかもしれない、といったような期待を持っている。
また、思春期まっただ中の中学部では、本校には高等部がないために進学先のことや、あるいはその後の「作業所」づくりに向けた取り組みといったように悩みはこれまでとは幾分変わってくるようである。あるいは、思春期の「問題行動」に悩んだり、「作業所」で求められるスキルを求めて、保護者はより現実的な側面に基盤を置く心理状態を持つようになる。保護者としては、現在の堺市の教育行政、福祉行政においては、もはや悠長な考えなど持つ余裕もなくなってくるのかもしれない。中学部も卒業に近づくと子どもの将来に関してはっきりと意見を述べる母親が増えてきたり、あるいは高等部に入学してからそのような傾向が見られてくる母親もいる。保護者もせっぱ詰まるのである。このことは、保護者の子どもに対する目標がはっきりすることで、ある意味では歓迎すべきこととしてもよいのかもしれない。教師との将来に関しての意見や考えに衝突が見られる場合もあるが、逆に協力体制が組みやすい場合も多い。
このような低学年、中学部に比べて、高学年での保護者の心理状態には何らかのちがいは見られるのだろうか。高学年期は子どもも学校に慣れ、保護者も学校のやり方になれてくる時期である。子どもを百舌鳥養護にやっておいてよかった、あるいはやっておけばどうにかなる、と考える保護者は少なくはないだろう。その背景には、子どもと保護者(特に、母親)の心理的な学校生活への慣れ、つまり、安心感と安定感があるのだろう。いきおい、子どもの将来像や学校教育への期待や注文が「現状維持態勢」になりかねない。
子どもの側では目に見えない思春期の波がおそいかけており、一刻もはやく実態をつかみ、対応を考える必要があるかもしれない。将来像もこの思春期をいかに乗り越えていくかに大きく関係しているかもしれないのである。身体の成長、肥満、性的な問題、自我のいっそうの表出、こだわりなどの「問題行動」、よりいっそうの落ち着き、大人びたしぐさ、などなどこの時期の変化を保護者がどのようにとらえ、理解し、将来へとつなげていくか。これは保護者だけでは解決できない大きな課題である。我々専門家の援助が必要なのは言うまでもない。
保護者に見られるこのような「現状容認的ないし満足的」な心理状態に、いかに教師が将来像を描いて、この子らが人間として生きていくかのテーマを提供するかが大切である。もっとも、このような援助を必要とする保護者の数はそう多くはないのかもしれないが。低学年、中学部との比較で私見を述べたまでである。
3.担当職員の側面[課題としての見通し、あるいは計画性]
高学年部は小学部の卒業式を担当する。6年生の卒業式において、「いよいよ4月からは中学生」という祝いのことばだけで本校の6年生児童全員が心身ともにそのまま中学部にすんなりとなじんでいくとは限らない。他の小学校からの入学者が内部進学者と同数に近い現在の中学部の状況を考えるとき、むしろ小学部と中学部での「集団の質」のちがいやそのために当然のこととして生じる指導のあり方のちがいにとまどう者が多いとも考えられる。したがって、高学年部においては、例えば5年生よりは6年生において、また、6年生においても1学期よりは2学期においての方が、やがて彼ら自身が置かれることとなる中学部という生活年齢集団に生活指導や課題設定のあり方の方向を向けていくことが必要である。本校高学年児童のような重度児(重度児だけでなく、むしろ軽度の遅滞児の方がやっかいな場合も多い)の場合には、「4月からは中学生」ということばだけでは中学部での学校生活への移行にかなりの無理を強いることも多いように思う。表面上は問題が少なく移行がなされているような場合でも、彼らの心身には相当のストレスとなりかねないのである。悪い場合には、そのようなストレスはある場合には「問題行動」となり表現されたり、不登校というような現象にもなりかねない。彼らはストレスを適当に回避したり、解決したりが苦手である。
そこで、彼らのストレスをできるだけ小さいものとしていくためには、担当教師やもちろん保護者が例えば5年生の後半くらいから、遅くとも6年生になった時点において、中学部への移行を見通した指導を計画的に考え、実践していくことが求められるだろう。この場合の指導とは具体的な課題の設定にとどまらず、思春期に突入しかかっている、あるいはもう突入している者に対して、それなりの心身の状況に見合った接し方をしていくことも含まれる。あるいは、そのような心身の状況に向けてまわりの大人が意図的にし向けていくような接し方をすることが必要である。なぜなら、そのような心身の状況は中学部での生活で遅かれ早かれ必ずやってくることだからであり、あるいは、そうすることで自分の置かれた状況への対処に自信を持って中学部での生活に移っていけるようになるからである。
このような思春期における心身の状況は、生物学的に必ず彼らに訪れる。これは避けられない事実であり、たとえ障害のあるなし、重度軽度を問わない。問題は表面上それがどれだけはっきりと見えるかどうかであって、もし明確に表面に現れてこない場合は、むしろ保護者や担当教師がそのような時期にある者として扱っていってあげることが大事である。それこそが、彼らの成長を喜び、大切にし、その人格を認めていくことになる。生活年齢上先に述べた「発達の第二の急進期」に突入するや彼、あるいは彼女はもう大人なのである。健常児は自分で大人への階段をさまざまな経験をしながら知らず知らずのうちに登っていく。同じ人間として障害を持った者がそのような階段を自分だけでは登れないなら、彼の人格を保証するためには、その形成をまわりが助けていく必要がある。生物学的に大人の仲間入りをした彼らを精神的に幼児段階に置くことは人格の分裂を招くことに他ならない。
高学年児童は知らずのうちに、このようなからだとこころの分裂の状態に置かれかねない。それはまわりの大人が助長している場合さえある(いわゆる「二次あるいは三次障害」の助長である)。それはことばを換えると、まわりが障害を助長していると言ってもよいだろう。特に保護者に対してはいつまでも子どもでないことを具体的な例をあげて説明していくことが必要である。身体が急速に伸びる時期であることは先に述べた。親が気がつかないうちにいつの間にかからだは大人になってしまっていた、といったこともあり得る。特に社会的なルールに関しては、高学年の初期あるいはそれまでに身につけておきたい。養護学校の中では当然のやり方であっても、学校の門を一歩出るともはや社会的な通念上許されないものであるようなことも多くあるようである。このようなことについて、部の会議で話し合う時間があってもよいのだろう。担当職員が社会と養護学校現場との橋渡しにならないといけないのだろう。養護学校職員というのは障害を持つ彼らの人格形成にかなりの責任を負っているのだと思う。養護教育というのは、とてつもなく奥が深いものであり、それに携わる教職員の専門性のひとつとして計画性といったものが非常に重要となってくる。